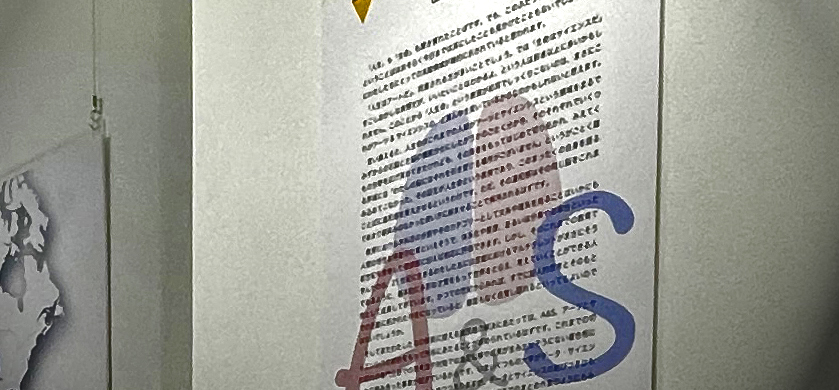「人生」も「生命」も聞き慣れたことばである。でも、このふたつを融合した「人生命」となると、これはおそらく今までは耳にしたことも見かけたこともないだろう。むろん辞書を引いてもでてこないしWikipediaにもない。ここにわたしたちにとっての未踏領域が端的に示されている。
「人生はアートだ」といえば、同意される方は多いだろう。では「生命はサイエンスだ」、すこしおかしな表現だが、いいたいことはわかるよ、という人は前者以上に多いかもしれない。このことから「人生命」という表現が初耳でしっくりこないのは、まさにこれがアーツ & サイエンシスの、ど真ん中を突いているからだと思えてくる。
言い換えると、人生命はこれまでの人類がアーツとサイエンシスという領域をまるでみずからの右脳と左脳の機能分化に沿うごとく分かち、そのそれぞれでいくつもの分野を広げ深めてきたけれども、その両者をもって切り拓かれ、みえてくる界域には「わたしらの脳にはそれを引き受ける部位がございません」というがごとく踏み込めずに棚上げ、ないし看過してきたのだろう、ということである。人生命という表現は、その証左であり、このまったくの自分自身を語ることが違和感を覚えさせるというわけである。
でも、そうであれば、その違和感は脳の大いなる可塑性のことを考えれば、そのあまり馴染みのなかった使い方に挑ませつづければ、空を飛ぶとか、目をこらしてウイルスを見ましょうといった無茶助とは違って、やがて解消される可能性は望める。
教育における学科目の分割やそのカテゴリーとして文系や理系を括ることはいかにも人間の悟性お得意の仕業といえそうで、体系化や整理、あるいは分業やわかりやすさ、それに依拠した効率性といった前世紀に華やいだ価値観に沿えば相応に評価できる。しかし、そのこれまでの教育で学んだのち、21世紀に生きているわたしたちには芸能におけるマルチタレントがまさにそうであるように、基本的に多彩な才覚をもち、あらゆる境界、括りの線引きを超えて世界をとらえ、考え、行動できる人間となっている。かつての世紀の当たり前の人間観からすれば、すでに超人的思考とそのもとでの活動に拓かれた存在になっている。そう臆面もなく自覚し語れるのではないだろうか。
すでにわたしたちはたとえば30年程前に『知能環境論』で語られた近未来の開放情報時空を事実上、手にして日々過ごしている。だから駅でも街中でもその端末から目を逸らさず、否、逸らせず危なっかしく歩く人たちが溢れている。それは視力補綴具としての眼鏡と同様に、記憶を主とする認知補綴具としてのスマホがわたしたちの神経機能に接合してしまったがゆえの後戻りできない変容をあらわしている。と同時にそのことは脳自体に担える部位を必要とせずとも自身の外部との連動次第で知性の振る舞いやありようは柔軟に変容できるという可能性を示してくれている。
だから、なにがなんでも脳の可塑性に頼り期待するといういわば頭脳求心主義に立脚せずとも、もはや頭脳遠心から脱脳化した種に特有の環界と接合した認識のありようは当たり前に働いているのであり、そのなかでこの世紀のわたしたちは日常を暮らしているのであって、その現実を再評価すればよい。それは決して多大な努力を要する大それたありようを語っているわけではなく、いまここの日常現実の素描にほかならない。その写し絵をあらためてみつめれば、わたしたちの神経系とわたしたちの環界を結節している要にテクノロジーがあることがよくわかる。
そのことは換言すれば、おのずともつ神経系とおのずからある環界に問題解決や未踏の界域に適するテクノロジーを導入すれば、解けずにいた課題は扉を開き、未踏世界は拓かれていくことを語っている。アーツとサイエンシスという人間が人間たるゆえんとなる営みが融合し人生命を真っ直ぐに進む道を開拓するとすれば、それはその環界としての場を設け、そこにアーツとサイエンシスを結ぶテクノロジーを投入することで果たされると見通すことができる。
アーツとサイエンシスの架け橋となるテクノロジーを渡たり、行き来するものは何か? いうまでもなく所与、データである。昨今、世を賑わし大学には学部まで新設されるほどのデータ・サイエンスなる概念はもとよりトートロジーでうっかりすると無限後退の非決定に陥る危惧さえ感じさせるものがあっておかしみを禁じえない。それよりも科学の地平のその先が問われているこの世紀と将来に人類の課題として求められているのは、みずからの知性による二大営為自身の橋渡しである。そのひとつがすなわちデータ・アーツ & サイエンシスである。その媒体にテクノロジーが架けられ、データがアーツとサイエンシスのあいだを行き交うことで、その結果としての形象がただどこかのサイエンスの蛸壺においてではなく、アーツへと展開されてかたちづくられていく。
だから、展覧会、そこはまさにその表象をわたしたちの社会に向けてエクスポーズする場としてはたらく。